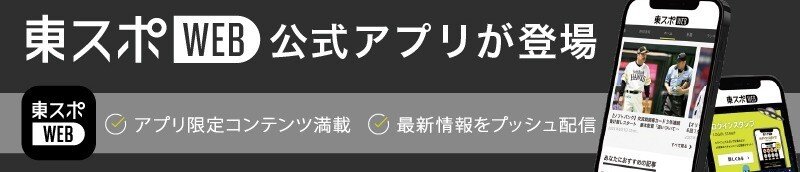ご存じでした?「ホルモン」の由来はギリシャ語、名付け親は生物学者スターリング
性は生なり!人々は何百年も前から睾丸が男らしさをつくることに関係していると気が付いていました。でもそれがどうしてなのかはハッキリと分からなかった。そこでその謎をいろいろな実験で解こうと挑んだのです。
1979年、ベルトルトという学者は、雄鶏の象徴であるトサカと睾丸の関係に目を向けてこんな実験を行いました。まず、雄鶏の睾丸を取り出したところ、トサカは小さくなった。

次に取り出した睾丸をその雄鶏のおなかの中に植え込むと、トサカの大きさが回復したのです。いったん切り取られ、ふたたび腹の中に埋め込まれた睾丸が、神経を通じてトサカと連携しているはずはない。つまり、睾丸から出るなんらかの不思議な物質が、血液などにまじってトサカまで運ばれて作用しているという仕組みに気づいた。この実験は、睾丸の内分泌学的な意義を初めて証明したと高く評価されています。
睾丸から出る不思議な物質がホルモンであり、ホルモンが働く仕組みを「内分泌」と呼ぶようになったのは20世紀初頭。ホルモンの命名者はイギリスの生理学者スターリング。語源はギリシャ語の「ホルマオ」すわなち、「刺激する」という意味に由来しています。そして、このホルモンを研究する学問は「内分泌学」と名づけられました。「内分泌」とは、涙や汗のように体の外に分泌される「外分泌」に対して用いられる考え方なのです。

ホルモンの研究がまず男性ホルモンから始まった背景には「若くありたい」「たくましくありたい」という『男性の夢』が色濃くうかがえるのは興味深いです。
熊本美加(くまもと・みか)医療ライター。男性医学の父・熊本悦明の二女。男女更年期、性感染症の予防と啓発、性の健康についての記事を主に執筆。