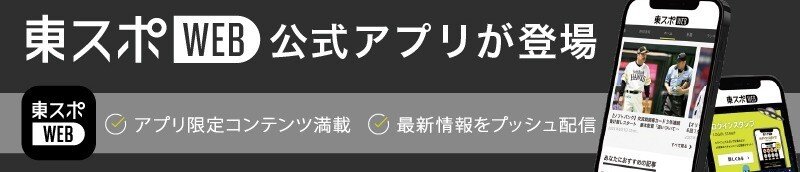身近に潜む「失礼の地雷」を踏まないために
取材する記者にとって最も憂慮すべきことは、自らの失礼によって話を聞かせてくれる取材対象者の気分を害してしまうことかもしれません。インタビュー中に「君、失礼な質問をするな」と直接指摘してもらえるのは、申し開きができるチャンスが残っているだけまだマシなほう。一番恐ろしいのは、自分がどんな無礼を働いたかもわからぬまま、相手の機嫌が悪くなり、取材そのものがなかったことになってしまうケースです。失礼という地雷は日常生活のあらゆるところに潜んでいますから、どんなにベテランになったとしても緊張感と無縁ではいられません。(東スポnote編集長・森中航)

最近やらかした失礼
かくいう私も取材対象者はもちろん、上司、同僚、友人、知人と周囲のあらゆる人々に数々の失礼をおかけしてきました。やらかし過ぎてnoteでは公開できないような失礼も多々ありました(苦笑)。話せる範囲で申し上げますと、最近はこんな失礼をしてしまいました。
大学時代の友人数人と久しぶりに飲んでいたときのこと。「YouTubeとかTikTokとか動画って強いよね。テキスト読んでもらうのしんどいわ~」といった会話をしていたのです。
友人A ショート系の動画ってスワイプで次々見るじゃん。でも、1分前に何を見てたか覚えてないんだよね!
私 わかるわかる。記憶と無縁どころか、情報を垂れ流しで摂取し続けるのって脳に悪影響なんじゃないかとすら思う。
友人A ウチの子供もタブレット渡すとずっとYouTubeを見てるわけ。将来ヤバイのかな。
私 大人でも意識しないとずっと見ちゃうもんね。そういえばジョブズも自分の子供にiPad使わせなかったって本に書いてあったの読んだな。
友人B ……あのさ、子育てしたことがない人が勝手に、YouTubeが子どもに悪いとか勝手なこと言わないでくれる? 共働きで育児もして、どうしても子どもを直接見てられない時間ってのがあるわけ。子どもって泣いたりケンカしたりただでさえカオスなわけだけど、YouTube見せている間はおとなしく座っていてくれて、こっちはその間にやらなきゃいけないことを片付けてるんだよ!!
突然、友人Bが怒ったのです。私が直接的に友人Bの育児スタイルに言及したわけではありませんが、地雷を踏んでしまったのでしょう。正直なところ「なぜコレくらいで俺にキレるんだ…」と思いましたが、久しぶりの再会を台無しにするのも大人の対応ではありません。「そんなつもりで言ったわけじゃないんだ。気を悪くさせてごめん」と詫びました。友人Bも駅で別れる際に「さっきはカッとなって悪かった」と言ってくれて、心のざわつきが消えました。取材現場じゃなくて本当に良かったとしか思えません。
石原壮一郎さんの『失礼な一言』を読む
さて、「大人力検定」で知られるコラムニスト、石原壮一郎さんが『失礼な一言』(新潮新書)という本を出しました。長らくお会いできておりませんが、私はかつて取材をさせていただき、「それができたら立派な大人だよな~」とうなるほどの対処法を毎回教えてもらった記憶があるので、どこか懐かしい気持ちで読み始めました。

それこそ失礼に当たるのかもしれませんが、石原さんにはほどよい脱力感があるのです。伊勢うどん大使だからかもしれません(笑)。厳密に「あれも失礼、これも失礼」と重箱の隅をつつくのではなく、相手が怒ってしまっても上手に流しましょうねというニュアンスが伝わってくるのです。
自分にとって不愉快な心配をされていると感じたときに、相手の失礼さに腹を立てたところで何も解決しません。気遣いという攻撃を繰り出して「一枚上手」になってしまうことが、心の平和を守る近道です。
本当に許せない言動はもちろん別ですが、会社の飲み会というのは、やる意味も含めて、大らかな気持ちで適当に立ち向かうのが、もっとも楽ちんで得るものも多いと言えるでしょう。
他人の仕事を見下してくるのは、「物事の表面しか見ていなくて、自分はそれに気づいていない」「プライドに不自由している」という点で、気の毒な人たちです。心の中で「かわいそうに」と同情してしまえば、たちまち優位に立てます。「何か嫌なことでもあったの?」と聞くのも一興。きっと相手は、さぞ複雑な表情を浮かべるでしょう。
「楽そうなしごとでいいね」と言われたときは、ニッコリ笑って「そう見えたとしたら嬉しいです」と返すのがオススメ。誤解をまともに受け止めてあげる義理はありません。「見下された……」と気にすること自体、自分の仕事に失礼です。全力でサラッと受け流しましょう。
というわけで全編にわたって大人になる(=地雷を堂々と踏まない)ためのエッセンスが詰まった一冊ですので、社会人1年目の方にもおすすめです。
時代とともに「失礼」も変わった
私が個人的に衝撃を受けたのが第5章にある『「失礼」の古典を読み返す』という項目でした。1970年に出版された『冠婚葬祭入門』という茶道家の塩月弥栄子先生が書かれた大ベストセラーを石原さんが振り返ることで、時代の違いがめちゃくちゃ鮮明になります。
【隣家からの騒音に悩まされるときは、同程度の音をだすとよい】
→隣家からエレキ・ギターやステレオの騒音が鳴り出したら、同じような大騒音を出すのがよい。そうすれば相手は非を認めて、騒音が収まるだろうとのこと。ご近所づきあいが濃かった時代には効果的だったかもしれませんが、今だと余計に険悪になる予感しかしません。
険悪どころか事件に発展してもおかしくなさそうですよね。昔は思った以上にワイルドな時代だったということです(笑)。過度に恐れ過ぎず、失礼と上手に付き合いたいものです。