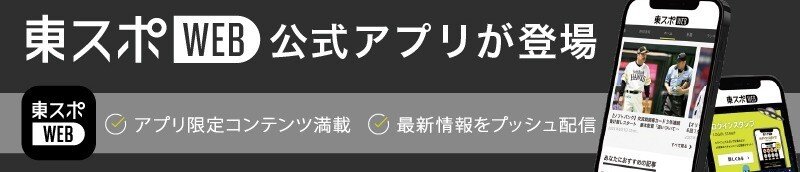まぼろしじゃない!地底深く眠り続ける黄金の城
埋蔵金研究の第一人者・八重野充弘氏のコラムをnoteで復刻! トレジャーハンティングの魅力と歴史の奥深さをご堪能ください。5回目はコチラ!
× × ×
岐阜県白川郷の帰雲城の財宝が広く知られるようになったのは、1972年に佐々克明氏が「まぼろしの帰雲城」を刊行してからだ。佐々氏は地元の郷土史家・松古孝三氏から、それまでは伝説でしかなかった城と城主・内ヶ嶋氏の存在が、信頼できる史料によって確かめられたことを聞く。

内ヶ嶋3代の手書きの書状が発見されたことで帰雲城の実在が裏付けられた
佐々氏の先祖は安土桃山時代の富山城主・佐々成政で、先祖が関係する話だったことも関心を寄せた一因だった。成政は豊臣秀吉と対立して敗れる。このとき、内ヶ嶋3代目の氏理は、成政側についた。ふつうなら領地没収のところ、おとがめなしだった理由は、同氏が武将というより鉱山技術者だったからだ。初代為氏は、足利義政の命でこの地に移り、氏理のころには付近に6つの金山と1つの銀山が開発されていた。
さて、危機を乗りこえた氏理が、祝宴を催していた最中の1585年11月29日深夜、推定M8・1の大地震が襲う。そして、庄川の東にそびえる帰雲山が山頂から崩壊し、大量の土砂がおそるべき速さで山麓に押し寄せ、城一帯を瞬時に埋め尽くしたのだ。

帰雲山の崩落した部分が今も生々しい
佐々氏は、城は鉱山会社のようなもので、中には鉱石から精錬途中のもの、出来上がった金塊まで、さまざまな形状の黄金があったという。それを信じる人も多く、価値は時価5000億円とも2兆円とも…。場所は現在の保木脇のあたりらしく、筆者も松古氏に案内してもらったことがあるが、土砂が堆積したあとは確認できたものの、城の所在地についてはまったく見当がつかない。
1973年ごろから断続的に調査が行われているが、進展はない。埋没した城と財宝は、相当深いところにあると見られるので、それをとらえるハイテクの機器の登場を待ちたい。

城があったと推定される場所に、碑と観音像が建てられている
やえの・みつひろ 山に、海に、眠れる財宝を探して47年!のトレジャーハンター、作家。日本トレジャーハンティング・クラブ代表。1974年、熊本県天草下島での財宝探しを開始。以後、日本各地の埋蔵金伝説を求めて全国30数か所を歩き、これまで実際に発掘を行った場所も10か所以上にのぼる。財宝探しや埋蔵金に関する著書多数。公式HPでは徳川埋蔵金を題材にした小説「リカバリー」も公開されている。